本記事では前回に引き続き、クイズ形式で心電図の理解を深めていきたいと思います。
Q6. 「脈が飛ぶ」と訴える患者さんの心電図は?

Q6. 解説
脈が飛ぶという訴えをどう考えればよいでしょうか。
ここでは、拡張期の時間に注目してみたいと思います。Aは正常洞調律の波形です。
心周期の点から、収縮期と拡張期に分けられます。拡張期は心室が拡張して血液を貯めこむ時間のことです。
拡張期の時間が短いと心室に血液を貯める時間が不十分であるために、次の収縮では空打ちになり脈は触れません。このとき、脈が飛ぶという訴えをされることがあります。
Cの心電図を見てみましょう。基本的にはAと同じ洞調律の波形ですが、上下を見比べてみてください。
第2拍目では予想される時期よりも早いタイミングで、ややQRS幅の広い波形が出現しています。これは心室性期外収縮という不整脈で、健常人でもよくみられますが、ここでは拡張期の時間に注目してください。
他の波形に比べると、拡張期の時間が短くなっていることが分かります。この際に、心室に血液を貯める時間が足りないために、次の収縮では空打ちとなり、「脈が飛ぶ」こととなります。
次にBの波形を見て見ます。RR間隔がバラバラ、その間の波形も不明瞭で、基線が揺れているように見えます。明らかなP波は認められません。これは心房細動という不整脈で、高齢者の多くに認められます。
ここでも拡張期に注目してみましょう。RR間隔がバラバラですので、拡張期の時間もバラバラです。2拍目(黄線)に注目すると、拡張期が特に短くなっていることが分かります。先述と同様の理由で、脈が飛ぶ可能性があることが分かりますね。
正解はBとCになります。改めて、収縮期と拡張期の意義を復習しておきます。
収縮期では心室が収縮し、全身に血液を送ります。拡張期では心臓を栄養している冠動脈に血液が流れます。
大事なことは、心拍数が変化しても収縮期の時間はほぼ変わらないということです。
例えば、心拍数80回/分から不整脈により160回/分に変化した場合を考えてみます。
心拍数が変化しても収縮期の時間が変わらないと説明しました。ではどうなるかというと、拡張期の時間が犠牲になっています。
このように、頻脈性の不整脈では拡張期の時間が短くなることに注意が必要です。
Q7. 心拍と脈拍の乖離を評価する方法は?
Q6では心電図の情報が既にありましたが、モニターがついていない状況もありえます。
心拍と脈拍の解離を評価したい際に、どうすればよいでしょうか。
また、その際の対応はどうすればよいでしょうか。

Q7. 解説
まず、心拍数と脈拍数が解離すると何が困るのでしょうか?
状況として、拡張期の時間が短いために両者の乖離があると先述しました。
拡張期の時間が短いと心室に充分な血液を蓄えられず、心室が収縮しても空打ちになっています。これは心室にとって非効率な仕事をしているということになります。
更に、拡張期は冠動脈に血液が流れるという重要な時間です。
拡張期の時間が短くなると、冠動脈に流れる血流が減少し心臓が虚血に至る可能性があり、危険です。
具体的な評価ですが、心拍数と脈拍数の解離はフィジカルアセスメントで確認が可能です。心拍は心音聴取、脈拍は橈骨動脈の触知でそれぞれ確認ができます。
従って、患者の脈を触れながら、聴診器を胸に当てて心音を聴取することが一つの方法になります。
心音は聞こえるけれども、脈は触れない…という際は、Q6で示したような、拡張期の時間が短くなる不整脈の存在が示唆されます。
またBの心房細動であれば、RR間隔が不整であり、脈の触れるタイミングが再現性をもってバラバラであることからも疑うことができますね。
心拍と脈拍の解離がある場合、薬剤での対応が検討されます。β遮断薬やCa拮抗薬などは心拍数を低下させる薬剤ですが、別の視点で考えると拡張期の時間を延長させる薬剤であるともいえます。特に血圧低下が認められる場合、使用を考慮してもよいでしょう。
Q8. 心房細動では、抗血小板薬と抗凝固薬のどちらが使われる?
もう1点、Bの心房細動で最も注意すべき事項として、心源性の脳塞栓症があります。細動とは1分間に350回以上の興奮を表しますが、このとき心房はほぼ有効な収縮をなしておらず、ただ痙攣しているのみです。
特に左心房内にある左心耳という箇所は血栓を形成しやすく、何らかの拍子で血流に脳へ運ばれ、脳血管を詰まらせる可能性があります。特に、48時間以上経過した心房細動では抗血栓療法を考慮する必要があります。
心房細動においては、抗血小板と抗凝固薬のどちらを用いればよいでしょうか?

Q8. 解説
抗血栓薬は2種類あり、抗血小板薬と抗凝固薬です。
前提として、動脈のような血流が速い環境では血小板が、静脈のような血流が遅い環境では凝固因子が血栓を形成します。
心房細動ではどうでしょうか。心房がほぼ動いていない≒血流が遅く、静脈のような環境→凝固因子が働く、と考えることができますね、
以上から心房細動では抗凝固薬を使用します。
内服薬ではワルファリンやDOAC(直接経口抗凝固薬)、注射薬ではヘパリンなどがあります。

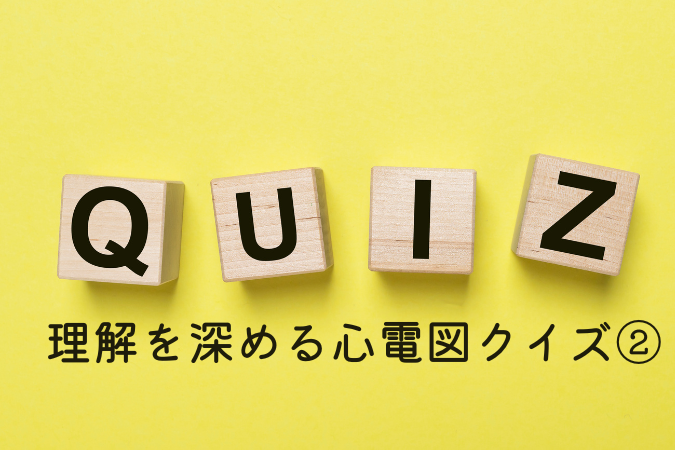
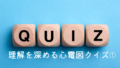
コメント