本記事では、クイズを通して心電図の理解を深めていきたいと思います。
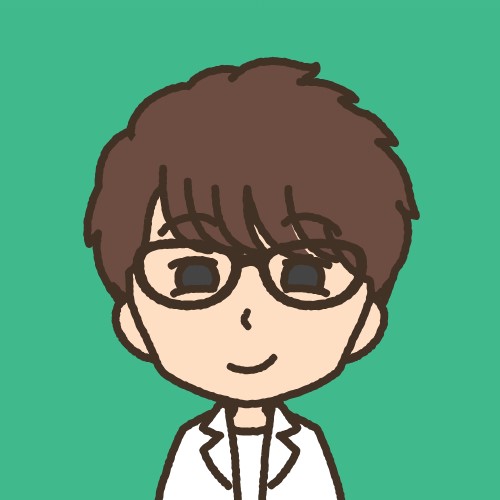
一部やや強引な設定にしているところもありますが、理解を深めるというところを第一の目的にしていますので、ご容赦ください。
Q1. 洞結節の脱分極はどこ?
下に解説がありますので、少し考えてからスクロールしてみてください。

Q1. 解説
P波はあくまで心房の脱分極です。洞結節の脱分極はP波より前になります。
洞結節や房室結節の細胞数は心房筋や心室筋などの作業心筋に比べて少ないため、体表面の心電図では観察することができません。
Q2. 血圧コントロールが良い波形は?
高血圧患者A,Bの心電図を以下に示します。アムロジピンを長期に処方されていたようです。心電図波形から、血圧のコントロールが良い方を考えてみましょう。

Q2. 解説
正解はBになります。
慢性的な高血圧があると、心臓はそれに打ち勝つ圧を常に生み出さなくてはいけません。
常に筋トレしているようなイメージでしょうか。心肥大が起こり、通常の心臓と比べると収縮に大きな起電力が必要になりますので、R波が増高するとされています。
さらに、左室肥大ではストレイン型のST低下といって、特徴的なST-T変化を示します。これは覚えておきましょう。
Q3. 不整脈発症が疑われる心拍数トレンドは?
A~Cのグラフについて、不整脈発症が疑われるものはどれでしょうか?またそれ以外のグラフについても、心拍数の変動の原因は何が考えられるでしょうか?

Q3. 解説
一つずつ見ていきましょう。
Aは一般的な日内変動の範疇です。
日中は交感神経優位のため、心拍数は上昇します。夜間は副交感神経優位のため、心拍数は低下します。
基線が揺れているのは体動や労作により一時的な心拍数が変動するためです。
Cは感染症で熱発した患者です。
発熱すると交感神経が徐々に亢進し、それに合わせて心拍数は少しずつ上昇してゆきます。
Bは頻脈性の不整脈を発症した患者です。グラフトレンドを見ると、18-21時の間で心拍数が急激に上昇しています。AやCのように生理的な経過では徐々に心拍数は変化しますが、不整脈は生理反射由来ではないため、急激に心拍数が変動するのが特徴です。
Q4. 薬剤性の徐脈性不整脈はどれ?

Q4. 解説
正解はBです。Q3と同じように考えると、Bでは21時過ぎで急激に心拍数が低下しています。生理的な経過とは考えづらいため、不整脈発症が疑われます。
Q5. β遮断薬使用後何が起きた?

Q5. 解説
β遮断薬使用後、心電図が房室接合部調律(ジャンクショナル・エスケープリズム)へ変化しています。
刺激伝導系の洞結節がβ遮断薬により抑制され、電気信号を作れなくなってしまっている状況です。その代わり、下位の調律である房室結節が調律を担っています。
房室接合部調律ではどのような心電図波形となるか考えてみましょう。
洞調律では洞結節がスタート地点で、心房→房室結節→心室へと電気信号が伝わります。
結果、P波→QRS波の順番で波形が出現します。電極(目)から見て、電気信号は近づいてくる方向に流れますので、P波とQRS波も陽性になります。
一方で、房室接合部調律の場合はどうでしょうか。
房室結節をスタート地点として、心房と心室へ同時に電気信号が伝わっていきます。
つまり、P波とQRS波がほぼ同時に出現します。
また電極(目)から見て、房室結節から心房への電気信号は遠ざかっていく方向へ伝わっていくため、P波は陰性になっています。
結果、上図のような波形になることがわかります。
本設問では簡単のために陰性P波をあえて目立つように配置しましたが、実際はP波がQRS波に埋もれて見えないことが多いです。
このように薬剤の副作用を心電図波形から確認できることがあります。

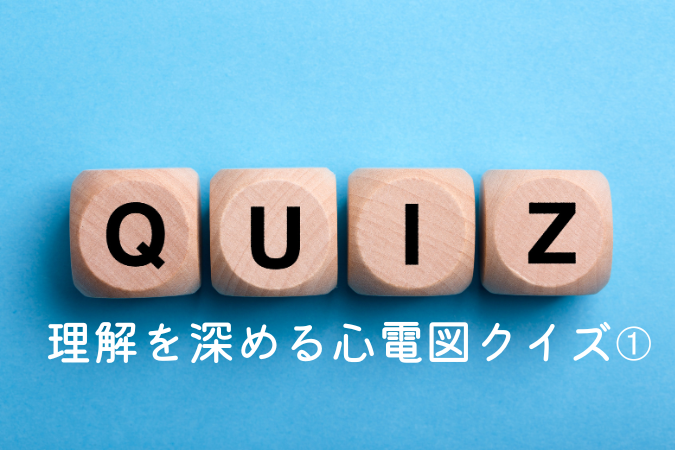

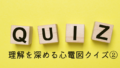
コメント