本記事では、ST部分の変化について説明します。
はじめに:QRS波・T波の成り立ち
前回の記事(QRS波とT波の関係について理解しよう)の復習です。
電気信号が心室へ伝わると脱分極を起こしますが、心室には1cm程度の厚みがあり、内膜側と外膜側で脱分極と再分極を起こす時間のずれがあります。
上図では未だ脱分極を起こしていませんが、最初に脱分極を起こすのは内膜側と外膜側のどちらでしょうか?
脱分極は内膜側から起こります。この際、+に帯電している内膜側と、-に帯電している外膜側で電位差が生じ、内膜側→外膜側へ電気が向かいます。電極(目)からすると電気が近づいてくるように見えることから、波形は上向きとなります。これはQRS波です。この後はどうなるでしょうか?
遅れて外膜側も脱分極を起こします。この際内膜側も外膜側も+に帯電していますので、電気の流れは生じません。したがって波形は上向きにも下向きにも触れず、基線上になります。ここが今回のテーマである「ST部分」になります。
ちなみにこの後どうなるかというと、外膜側から先に再分極を起こすのでしたね。
この際、電極(目)からすると内膜側→外膜側と電気が近づいてくる方向に流れますので、上向きのT波が生じます。詳しくは以下の記事を参照してください。
ST部分の正常と異常
話を戻します。ST部分が基線上に存在する理由は、心室の内膜側と外膜側の両方が脱分極を起こしており、電位差がないためです。
つまり、内膜側と外膜側の両方が「問題なく脱分極を起こす」ことができれば、ST部分は基線上から変化することはありません。
一方で、実臨床ではST低下やST上昇に遭遇します。見ての通り、これらはST部分が基線上にありません。
ということは、心室内に脱分極を起こせていない心筋細胞の存在が予想できます。
一つずつ見ていきましょう。
ST上昇時には何が起こっている?
まずST上昇からです。
結論から述べると、ST上昇は「大きな」血管が詰まっていることを示唆します。
大きな血管が詰まるとは、医学的には貫壁性の虚血と表現されます。
貫壁性とは、心内膜~外膜までの全層のことを指します。
前提として、虚血を起こした部位は脱分極を起こすことができません。
上図を参照してください。
周囲の元気な細胞は脱分極して+に帯電しています。一方で虚血を起こした細胞は脱分極できず、-に帯電したままです。このとき、電極(目)から見て虚血部位に電気が近づいてくるように見えますので、ST部分は上昇することが分かります。
このように、ST上昇は貫壁性の虚血の存在を示唆します。心筋梗塞が例として挙げられます。その他にもST上昇を来す疾患は存在しますが、まずはST上昇を起こす機序を理解してください。
ST低下時には何が起こっている?
次にST低下についてです。
こちらも心筋細胞の脱分極異常が起きているものと予想されます。
STが低下しているということは、電極(目)から見て遠ざかる方向へ電気が流れているのでしょうか。
勘の鋭い方はお気づきかもしれませんが、ST低下では心内膜側の虚血を示唆します。
外膜側は脱分極して+に帯電していますが、内膜側は虚血のために脱分極できず、-に帯電したままです。このとき、外膜側→内膜側に電気の流れが生じています。電極(目)からすると遠ざかる方向に電気が流れますので、ST部分は低下します。
ではなぜ心内膜の虚血が起こるのでしょうか。
心臓を栄養している冠動脈は、心臓の外膜側を走っています。外膜側に幹となる血管があり、分岐して内膜側に入っていきます。
冠動脈の虚血が生じた際に影響を受けやすいのはどちらかというと、分岐して血管が細い内膜側であることがわかります。
心筋梗塞のように冠動脈が根元から閉塞するほどの虚血であればSTは上昇しますが、狭心症のように部分的な虚血を生じる際は、ST低下が起こる可能性があります。
ST低下の要因は虚血以外にも…
虚血によるST低下の機序は理解できましたか?
一方で、ST低下は虚血以外にも様々な要因で生じます。
代表例としては高血圧による心肥大、低K血症、ジギタリス中毒などです。
これらのST低下の機序を説明することは難しく、未だ分かっていない部分が多いです。
少なくともST低下に関しては、ST上昇ほどの緊急性はありません。その代わり、立ち止まって様々な要因を鑑別に挙げて検討する必要があるでしょう。もちろん薬剤も影響している可能性があります。
代表的なST-T変化の波形
代表的なST-T変化の例を下図に示しました。
原因によってSTの変化の様子が異なることが分かります。
ややこしいなと思われるかもしれませんが、ある程度は覚えるしかないところもあります。
逆に、これらの心電図から病態把握のきっかけにできる可能性もありますので、一つずつ整理していけると良いですね。

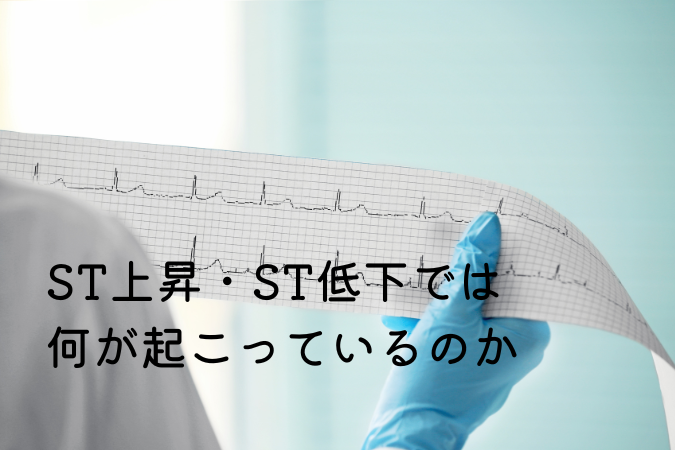
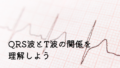
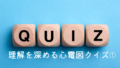
コメント